
2024年3月20日午前、「朱鹮杯」中日友好大学生訪中団一行15人は中国駐新潟総領事館の依頼を受け、大連理工大学を訪問しました。中国駐新潟総領事館の柏燕秋領事はイベントの初心を説明し、中日友好交流の重要性を強調しました。国際合作交流の王珏処長は訪中団を歓迎し、学校の状況を紹介しました。訪中団は来校後、キャンパスツアーやクイズコンテストなどを行い、中日の学生は日本語学科主任の指導のもと、グループ討論を展開し、...

3月18日午後、化工学院は日本学術振興会(JSPS)北京代表処を知順楼F213に招待し、プロジェクト紹介交流会を開催しました。国際合作交流処及び多くの学院から40名余りの教職員と学生が参加し、化工学院の刘毅副院长が司会を務めました。会議では、王珏氏、刘涛氏や山口英幸氏が学校とJSPSとの縁を振り返りながら挨拶をしました。JSPS北京代表処の金子惠副所長は資助プロジェクトを説明し、蘇媛氏と賓月珍氏はプロジェクトを申し込ん...

北京大学及び第13回中日学長フォーラムの主催者である広島大学の招待に応じ、張馳副学長は代表団を率き、11月28日から12月2日にかけて日本で開催された第13回中日大学学長フォーラムに出席し、「ゼロカーボン社会の構築:クリーンエネルギー技術革新」と題する基調講演を行った。本校の教務処、大学院、国際協力交流処、大連理工大学-立命館大学国際情報ソフトウェア学院(DUT-RU ISE)の関係者が同行した。代表団一行6人は立命館大学を...

2023年は『中日平和友好条約』締結45周年である。中日ハイレベル人文交流協議メカニズムの内包を更なる豊富化、及びに両国の高等教育分野における交流と協力の推進を目的に、本校の羅鐘鉉副学長は、中国教育国際交流協会の招待に応じ、代表団を率き、日本で2023年11月13日から17日にかけて開催された「第9回中日教育交流会」に参加し、「新時代における中日教育交流の革新と発展」と題する基調講演を行った。本校の国際協力交流処、...

10月30日、英国レスター大学のNithan Canagarajah学長、Sarah Davies副学長一行が本校を訪れ、大連理工大学レスター国際学院共同管理委員会会議に参加し、両校間の交流と協力を深めた。本校の党委員会の項昌楽書記とNithan Canagarajah学長一行は両校の協力強化について会談し、両校の協力分野の拡大、学院の発展に適した教員モデルの模索、科学研究協力の深化などについて検討し、意見を交換した。羅鍾鉉副校長、占敬敬学長補佐、国際協力交流処関係者が...
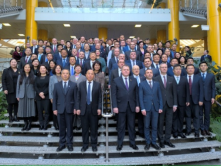
「一帯一路」教育活動の共同建設をさらに推進し、中国とベラルーシ両国の大学間交流と協力を持続的に深化させ、国際教育協力の新たなモデルを構築するため、大連理工大学は教育部の支持と指導のもとで、2022年下半期に中国・ベラルーシ大学連盟の設立準備を開始し、ベラルーシのミンスクで2023年11月21日に設立式、22日に学長フォーラムを開催した。同連盟には40校の中国側学校、14校のベラルーシ側学校を含み、両国の各分野のトップ...

10月27日、「世界の力を集め、人材の育成を助け、持続可能な未来を共に創造する」フォーラムが大連理工大学と「ダブル一流」建設大学国際交流分会の共同主催により、北京国際会議センターで順調に開催された。これは第24回中国国際教育年次カンファレンス&エキスポ(CACIE2023)の期間中に開催されたフォーラムであり、中国及び世界各国の教育関係者と各界の代表に知恵を授け、交流·協力を促進し、資源融合のプラットフォームを提供し...

10月23日、ハルビン工業大学が主催する「2023中露大学学長フォーラム」がハルビンで開催された。教育部と黒竜江省の関連指導者、ハルビン市党委員会書記・ハルビン市市長の張起翔氏、ハルビン工業大学学長の韓士傑院士、サンクトペテルブルク国立大学のユーリ・ペトロフ院士、バウマン記念モスクワ国立技術大学のアレクサンドロフ・アナトーリイ主席、華中科学技術大学の尤政学長、マカオ大学の宋永華学長らがフォーラムに出席した。...

中国高等教育学会とアラブ大学協会の招待に応じ、本校の国際協力交流事務所及び機械工学部の代表は2023年9月18日から2023年9月20日にかけて、ヨルダンのアンマンを訪問し、「中国・アラブ大学連盟交流メカニズム」の設立会及び中国・アラブ高等教育フォーラムに参加した。会議では、本校及び北京大学、上海外国語大学は「協力計画」の代表大学として、中国・アラブ大学連盟のアラブ側の主導大学であるヨルダン大学と大学間協力協定を...

2023年9月5日から14日にかけて、「連理同行、共話未来」中日同窓友情サマースクール――『中日平和友好条約』締結45周年の青年交流記念イベントが大連で開催された。当イベントは日本の青年学生に中国文化と先端技術を理解してもらうと同時に、本校の科学研究と教育の実力を示し、日本の学生の長期的な中国留学を誘致することを目的としている。日本の大阪大学、名古屋大学、東京工業大学、九州大学など10校からの105人の教員と学生が...